素読み校正とは?わかりやすい文章に改善する素読み校正4つのチェック方法
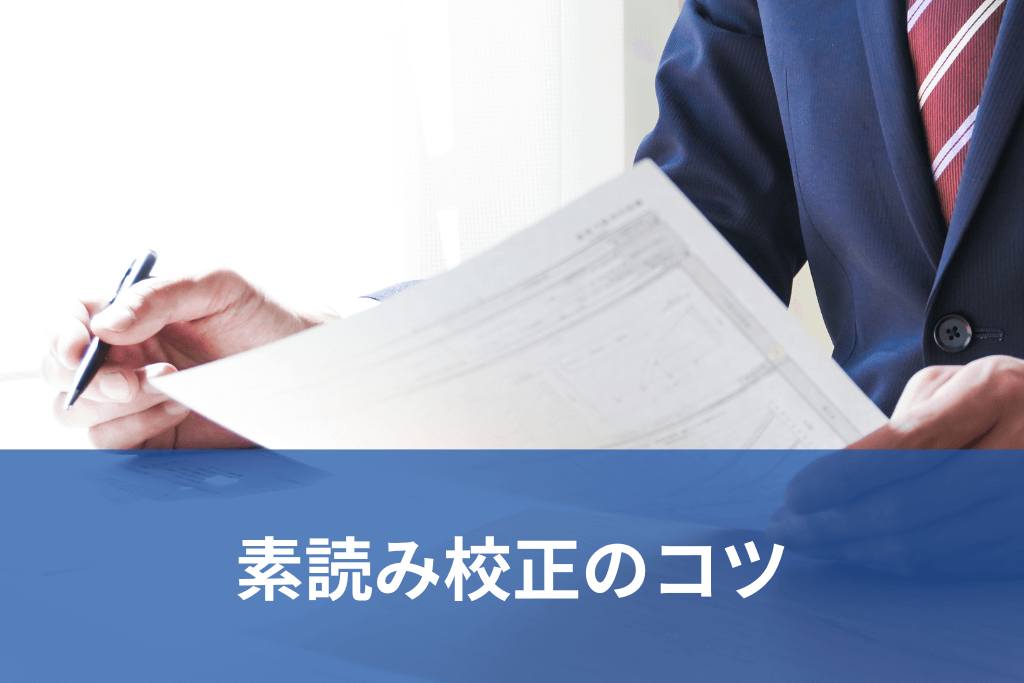
せっかく苦労してカタログやパンフレットを制作しても、いざ出来上がりを見てみると…

ここ他と表記が違ってる……
あれっ、ここ事実と違う……
きちんとチェックしていたつもりでも、表記の不統一や事実関係の誤り、誤字脱字など、
理想の制作物を作るのも簡単ではありません。
そこで重要なのが素読み校正です。
ダンクはカタログやパンフレット・チラシなど、さまざまな媒体の素読み校正を行ってきました。
この記事では、校正作業の中でも素読み校正に特化して解説しています。
制作物の精度を上げて、誤解も間違いもない販促物を作りましょう!
<対象となる制作物>
- 商品案内やガイドブックなどのパンフレット
- 商品やサービスを掲載するカタログ
- 案内や告知などのチラシ・フライヤー
- WEBサイトの記事など
「ミスが減らない」「内容をチェックする時間がない」でお困りの企業さまは、ダンクの校正・校閲サービスをご活用ください。
>ダンクの校正・校閲サービスはこちら
素読み校正とは
素読み校正とは、文章の誤りや一般常識の間違い、表記ゆれや誤字脱字などを見つける作業をいいます。
いわゆる「校正」とは作業内容が少し異なります。
校正は用意された原稿をもとに、原稿どおりに正しく制作されているかチェックする作業です。
対して素読み校正は、出来上がった紙面(以降、校正紙)だけをじっくり読みこんで、矛盾や誤りを見つけていく作業です。
(「校閲」に近い作業です)
この記事では、素読み校正のコツを解説します。
「校正」のコツは別の記事にまとめています。参考にしてください。
あわせて読みたい
素読み校正 4つのチェック作業
素読み校正の作業は、以下4つに大別されます。
素読み校正4つのチェック作業
- 常識チェック
日本語の違和感や常識的な間違いをチェック - 誤字脱字チェック
漢字や送り仮名の間違い、英語のスペルミスなどをチェック - 表記ゆれチェック
同じ制作物内で表記がゆれていないか(異なっていないか)をチェック - ファクトチェック
数値や時系列、日付や人名など事実関係の間違いをチェック
ひとつずつ解説します。
ダンクの校正ノウハウをまとめたマニュアルを無料提供しています。
校正全般のテクニックを、網羅的に体系立てて解説しています。
>校正の教科書 無料ダウンロード
常識チェック
ダンクが素読み校正を行う際に、最も注力しているのが常識チェックです。
校正紙を読んで常識の範囲で徹底的に矛盾や間違いを洗い出していく、重要な作業です。
以下のような視点で素読み校正することを、ダンクでは常識チェックと呼んでいます。
- 日本語表現
- 読者目線
- 整合性
日本語表現
まずは、日本語の表現として違和感がないかを素読みします。
いわゆる「てにをは」の表現や文法的な間違いを確認します。
読みづらい文章では、そもそも読んでもらえませんからね。
以下のようなポイントを意識して素読みします。
- 意味が通る文章になっているか
「てにをは」の使い方を間違えると、文章が読みづらくなったり、辻褄が合わなくなったりします。
正しく「てにをは」が使われているかチェックします。 - 一文が長くなりすぎていないか
一文に書く内容はできるだけひとつにします。
「なんか理解しづらいな」と思ったら、文を区切れないか検討します。 - 主語と述語は正しく対応しているか
主語と述語の係り受けは、正しくかみ合うようにします。
主語と述語だけを抜きだしても、意味が通じる文になっているかチェックします。
他にも日本語表現をチェックするポイントはいくつもあります。
以下の記事で、わかりやすい文章の書き方を解説していますので、参考にしてください。
関連記事|例文で解説!わかりやすい文章の書き方【ビジネス文書の作り方】
読者目線
想定読者を意識して、読者目線で素読みすることも重要です。
スーパーのチラシであれば夫婦世帯、業務用食材のパンフレットであれば飲食店、といった具合に媒体によって読者は異なります。
読者の目線になって読んでみると、普通に素読みをしても気がつかない間違いを発見することができます。
例えば、
ダンク印のお茶(2L) 1本140円 1箱(18本)2,160円
この商品情報におかしな点があります。どこか分かりますか?
答えは18本。
18本の箱入りがあったら重くて運べません💧。
正解は
ダンク印のお茶(2L) 1本140円 1箱(6本)720円
などになるはずです。
スーパーに買い物に行く主婦の目線で素読みすると、この点に気づくことができます。
ただし、読者目線で読むと言っても、これがなかなか難しい。
素読み校正を何度か経験して身につく技術だったりします。
(この視点で指摘できる人は校正の上級者)
以下から素読み校正の演習問題をダウンロードできます。自身の読者目線レベルを試してみるのも面白いですよ。
もしくは、対象に近い人が回りにいれば、読んでもらうのもオススメです。
自分では気がつかないところを指摘してもらえると思います。
誇大広告に注意する
読者目線で読んでいると「こんなこと断言していいの?」という疑問が浮かんでくるときがあります。
ない風呂敷を広げて誇張された表現、いわゆる誇大広告と言われるものです。
例えばこんな表現。
- 世界一、日本一
- 世界初、日本初
- 唯一
- 絶対
何かしらの根拠があって使用するのはいいのですが(第三者機関による調査結果など)、ない場合は「本当に使って大丈夫?」と疑った方がいいでしょう。
安易に誇張表現を使ってしまうと、信用を失うだけではなく、大きな損害につながる場合もあります。
(罰金や業務停止命令の対象になることも)
「知らなかった…」ではすまされません。最大限の注意をはらいましょう。
整合性
整合性チェックとは、同じ制作物の中で同一であるべき情報が、異なった内容になっていないか、異なった表現になっていないか、を照合する作業を言います。
例えば、「写真と商品スペック」「見出しと本文」「商品スペックとコピー」などの照合です。
修正を繰り返していると、あっちとこっちで言っていることが食い違う、整合性がズレるということが頻繁に起こります。
例えば以下のような事象。
整合性のズレに気がつきますか?

商品名を見ると「3ドア」ですが、写真は「2ドア」になっています。
これはわかりやすい例ですが、制作物を作る過程では、思いもよらぬところで整合性のズレが起こります。
ですが、整合性のチェック(照合できる箇所を徹底的に照合する)さえ忘れなければ、たいていのことは気がつきます。
上の例でいけば、商品名と写真の照合さえしていれば気づきますよね?
何となく素読みをしていてもなかなか気がつきません。整合性をチェックするクセをつけましょう。
誤字脱字チェック
どんなにわかりやすい制作物だったとしても、誤字脱字があっては信用を失ってしまいます。
誤字脱字をチェックするコツは「作業を分けて、ひとつひとつ読む」
これにつきます。
人間は機械ではありませんので、一度に複数のことを行うと、必ずと言っていいほど何かが抜け落ちます。
ですから、前述した常識チェックと誤字脱字チェックは別作業にして、誤字脱字をチェックするときは、それだけに集中しましょう。
誤字脱字チェックの精度を上げる方法は、以下の記事を参考にしてください。
あわせて読みたい
表記ゆれチェック
「お問い合わせ」か「お問合せ」か(送り仮名の「い」と「わ」があるかないか)。
送り仮名の有無や言い回しの違い、漢字表記かひらがな表記かなど、表記ゆれにもさまざまな種類があります。
いつの間にかこっそり存在している表記ゆれ。これをチェックする方法は大きく2つあります。
- デジタルツールで表記ゆれをチェックする
表記リストを用意してデジタルツールでチェック。確実で早い方法です。 - 目視で表記ゆれをチェックする
デジタルツールだけでは不十分。人間の目(目視)でチェックしてヌケモレを拾います。
ダンクがオススメしているのは、デジタルツールと目視によるハイブリッド型です。
どちらかだけに頼ると、すべての表記ゆれを防ぐのは難しい。
以下の記事で詳細に解説していますので読んでみてください。
ファクトチェック
ファクトチェックというと歴史的事実や時系列、引用の根拠など、事実関係の確認作業をイメージすると思います。
ダンクでも素読み校正を依頼された際は、事実関係の確認を行います。これはプロによる難易度の高い作業です。
ですが、本記事で対象としているパンフレットやカタログなどでは、ファクトのミスが発生しやすい項目はいくつかに絞れます。
かつ誰にでも、すぐに調べることができる項目です。
以下の記事で、ファクトチェックでミスが発生しやすい項目をまとめています。
あわせて読みたい
複数回に分けて作業を行う
素読み校正のコツをお伝えしました。
ポイントは以下の4つ。
素読み校正4つのチェック作業
- 常識チェック
- 誤字脱字チェック
- 表記ゆれチェック
- ファクトチェック
見るべき範囲は多岐に渡ります。
一回の素読みで、すべてをチェックするのは至難の技です。
ダンクでは、チェックする項目を整理して、最低でも2回に分けて素読み校正を行います。
(多いときは3回を超えます)
一回ですべてをチェックしようとすると、必ず何かを見落とします。
よくばらずに複数回に作業を分けて、素読み校正を行いましょう。
しかし、「すべては見切れないな…」と感じた方は、自社で必要となる項目は何か、を考えてみるとよいでしょう。
自社内で「クレームがついている内容」「問題となっている内容」はどれでしょうか?
- 内容の間違い、矛盾
- 誤字脱字の多さ
- 表記の不統一
- ファクトのミス(事実関係の誤り)
自社の状況に合わせて、必要な項目の素読みだけを行ってみてください。きっと、制作物の精度が上がると思います。
ダンクでは、さまざまな業界・媒体の素読み校正を請け負ってきました。
社内で素読み校正するのは自信がないと感じた方は、ダンクの校正・校閲サービスをご利用ください。
\「まちがい」を無くしたい方へ/
この記事を書いた人

- 株式会社ダンク 取締役相談役
- フリーランスでの編集・カメラマンなどを経て、1994年に株式会社ダンク入社。校正、進行管理、営業対応などに携わる。
2008年10月~2023年5月まで株式会社ダンク取締役社長に従事。
2014年からは、宣伝会議の「校正・校閲力養成講座」講師を担当。
販促会議デジタルマガジンに「販促ツールの品質を高める 校正のチェックポイント」などを寄稿
最新の投稿
「校正の教科書」を無料でダウンロード
ダンクの校正現場で実際に使っているノウハウをまとめました。この資料で「プロの現場レベルの知識」が身につきます。
販促物の校正の基礎と実践的なテクニックを学んで、 貴社の実務に役立ててもらえると嬉しいです。
以下のフォームにご入力いただき、「無料でダウンロードする」を押してください。
ダウンロードページにて、ダウンロードいただけます。



